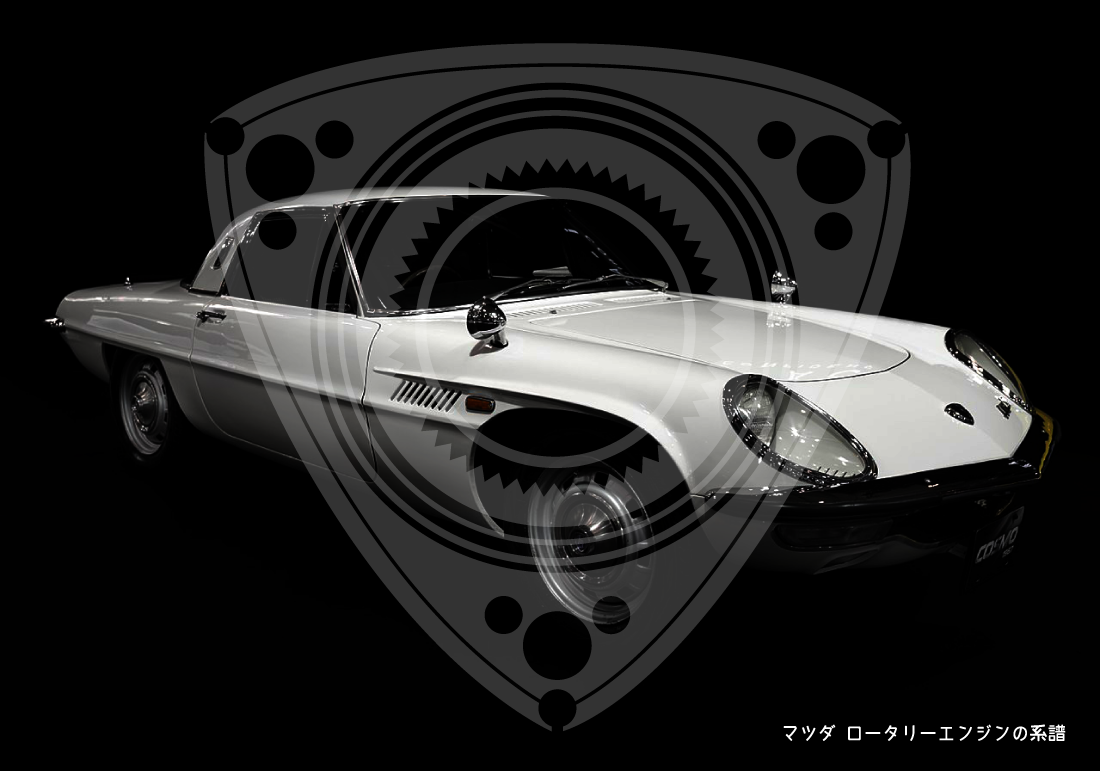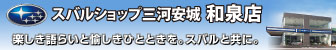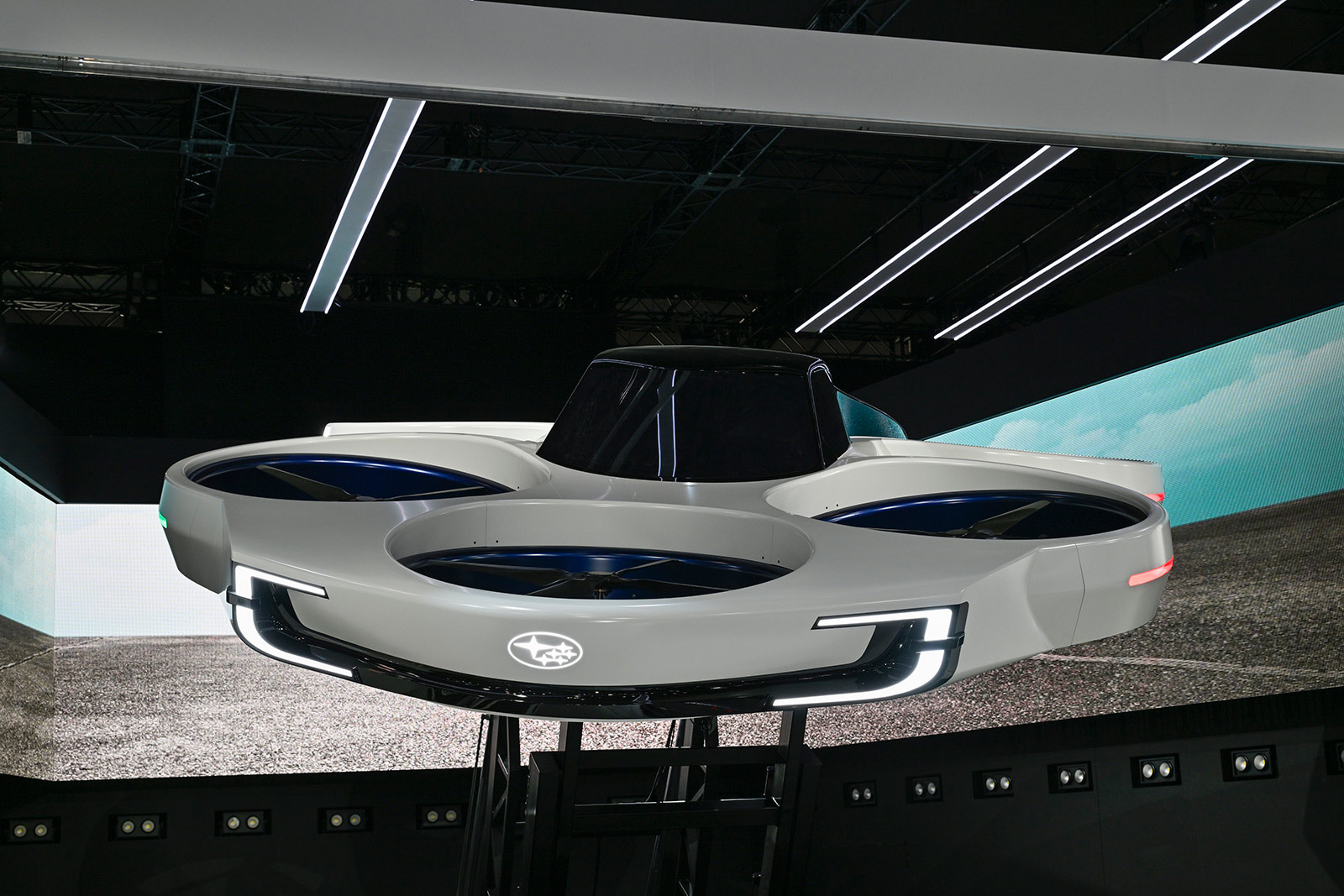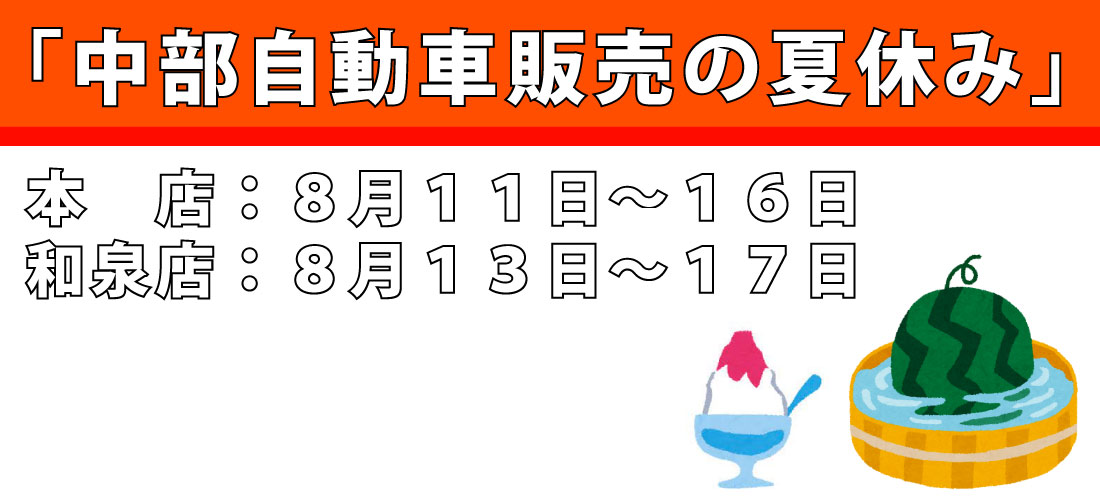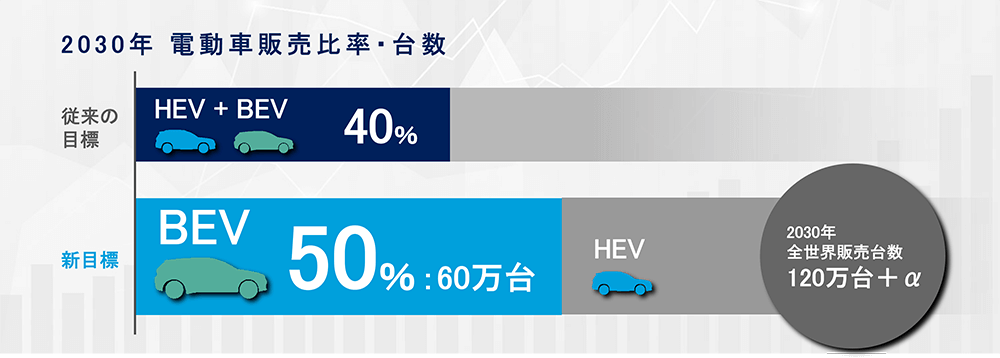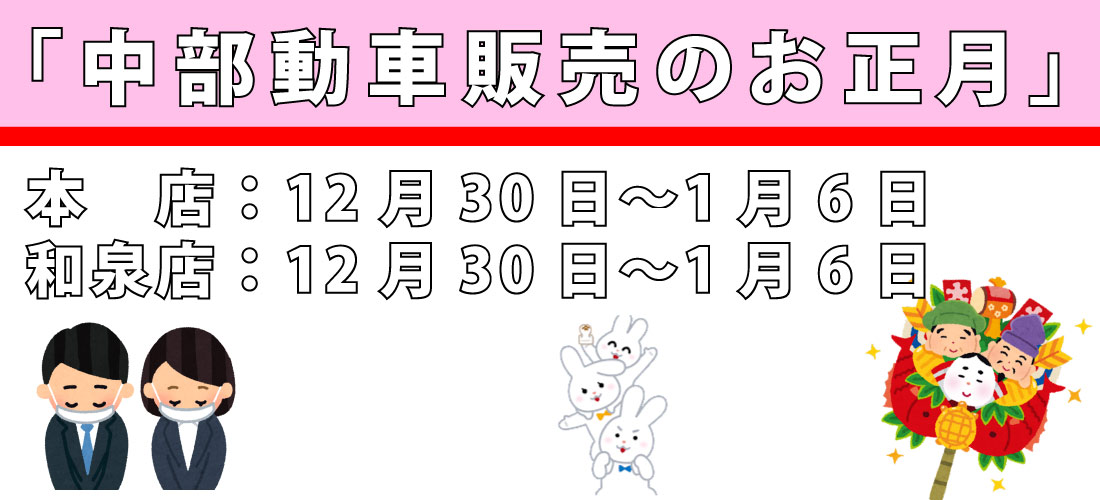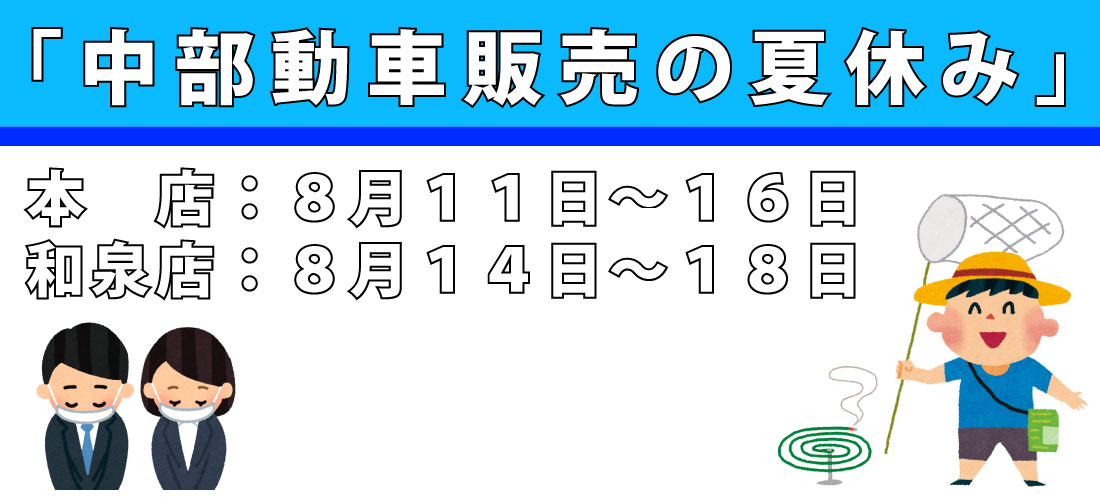スバルショップ三河安城の最新情報。スバルのヒストリー外伝「プリンス自動車〜消えるべくして消えた、スバルの兄弟〜」 | 2018年8月8日更新



ニュース ピックアップ [ スバリズム ]
2021年03月28日 クラブ・スバリズム
2021年03月22日 和泉店
2021年03月04日 クラブ・スバリズム
2020年12月26日 スバル
2020年09月16日 クラブ・スバリズム
2020年07月14日 クラブ・スバリズム
2020年06月16日 クラブ・スバリズム
2020年04月25日 クラブ・スバリズム
モータスポーツへの挑戦〜運命を決した、第1回日本グランプリでの大惨敗。〜
日本のモータスポーツの胎動。

1958年に海外ラリーに挑戦した、ダットサン1000「富士号」。
I, 天然ガス [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons
今から、遡ること60年。プリンスの面々は世界を目指していました。かつて、世界の列強と肩を並べて空を闘った技術者たちですから、世界と闘うことにためらいなど微塵も無かったのです。
彼らの運命は、第1回日本グランプリの大惨敗で決していました。しかし、彼らの情熱の行方は、決してはいなかったのです。
1960年代初頭、F1ではすでにミッドシップ革命が起こり、イギリスのロータスやクーパーが大活躍を演じていました。ドライバーはF1黎明期の世代から新旧交代の頃であり、ジム・クラークやグラハム・ヒルが徐々に頭角を現しつつありました。一方のスポーツカーレーシングは、フェラーリの一人天下。今日数十億で取引されている名車の数々が、鮮やかに駆け抜けていました。
一方、その頃の日本では、大小様々なメーカーが熾烈な販売合戦を繰り広げていました。その中から一歩抜け出そうと思えば、他社に対する優位性を示すのが一番です。そこで各メーカーは、国内外の様々なモーターレーシングに挑戦するようになります。まだまだ、初陣。初心者甚だしい時代のことです。国内レースを完走するだけでも、海外メーカーと一緒にレースに出場しただけでも、はたまた海外の有名サーキットの前まで行っただけでも、それだけで充分宣伝になったのです。
世界一流を目指すために、モータスポーツを志向したプリンス。
1961年の全日本自動車ショーで、プリンスは日本初の本格的スポーツカー「スカイライン・スポーツ」を発売。最大の特徴は、魅力的なデザイン。本場イタリアのミケロッティに委託したものでした。このモデルは、製造方法もカロッツェリアのそれに倣ったものでした。つまり、1台1台が手作り。手間がかかるため、総生産台数は60台ほどに終わります。兎にも角にも、世界に肩を並べる性能を標榜する自動車メーカーを目指して、プリンスはその第一歩を踏み出したのです。
自動車史を見れば明らかなように、技術を磨くにも、その技術を証明するにも、そのブランドを確立するにも、モータスポーツはもってこいの存在です。プリンスの面々が、自らのプロモーションの場にモータスポーツを志向したのは極自然なことでした。
そもそも、戦時中に国家防衛を担っていたプリンス技術陣の面々には、国内の自動車レースなど容易いと考えていました。「機織屋」のトヨタや日産に敗北するなどあり得ない話でした。
1963年5月、本田宗一郎お得意の無謀な計画の末に完成したばかりの鈴鹿サーキットで、FIA、JAF公認の本格的自動車レース「第1回日本グランプリ」が開催されることになります。日本で初めての本格的自動車レースとあって、大いなる関心が集まります。
真面目一本の旧中島の面々。見事に出し抜かれて惨敗を喫する。
ところが、当時は高嶺の花だった自動車。それをオモチャにしてレースをするなど日本の生活水準からは考えられないことでしたから、開催が決まっても各メーカーは冷たい態度に終始していました。その結果、日本自動車工業会の申し合わせとして、メーカーは一切の協力をせず全てをユーザーの手に委ねることとなります。
トヨタにしろ、日産にしろ、表向きはそのようでしたが、実際は違っていました。日本中の衆目を集める記念すべきレースで、一方的に惨敗することはメーカーの業績を大きく損なうことを見抜いていたのです。
車両規定を決めるにあたっては、我田引水を図るためトヨタと日産は強硬な態度に終始します。中小メーカーに過ぎないプリンスは、同意せざるを得ませんでした。車両はほとんど改造を許されず、特にエンジンとサスペンションはノーマルのままとされました。
結局、この申し合わせを忠実に守ったのは、旧中島の面々だけでした。プリンスと富士重工は、市販車で遥かに凌駕する競合に大惨敗を喫することになります。
レースが近づくと、各メーカーは鈴鹿にレースカーを持ち込んでテストを開始します。プリンスのタイムはライバルを大きく下回っていました。どう見積もっても、パワーの劣るはずのメーカーにいとも容易く置いていかれるその姿に、中川は敗北を確信します。と同時に、申し合わせ事項を遵守したのだから敗北も致し方なしと考えていました。
大惨敗で売却を決断した石橋と、忠実に翌年の雪辱を誓った中川。
結果は、想像通りの大惨敗。中川は、この時やっと自分自身がお人好し過ぎたことに気付くのです。
社長の小川は想像を絶する大惨敗のショックで鈴鹿からの帰途に脳貧血で倒れ、翌日東京に戻った中川は石橋に呼びつけられ、散々に怒鳴り散らされる始末。中川は、翌年の雪辱を石橋に誓うしかありませんでした。
そして、恐れていたことが現実になります。クラス優勝を遂げた各メーカーは、華々しく一大キャンペーンを開始。その優位性を強く形振り構わずアピールします。技術的優位性を個性にしてきたプリンスにとっては、特に手痛い結末となります。
この大惨敗の結果、石橋はプリンスの経営に興味を失い、日産への売却へと密談を進めていくことになるのです。
若き技術者の挑戦。〜スカイラインの父と呼ばれた男、桜井眞一郎。〜
自らの裁量を活かすべく、たま自動車に入社。

前列左から2人目が、桜井眞一郎。1954年撮影。
By 桜井眞一郎 [Public domain], via Wikimedia Commons
スカイラインの父、後にそう呼ばれた男がいました。櫻井眞一郎です。無類の機械好きだった櫻井少年は、1929年生まれ。近くに日本通運の車が来た時に膝の上に乗せてもらって以来、完全に自動車の虜になっており、排ガスの臭いを嗅ぐためにオートバイの後を追いかけるほどでした。
戦時中は、学徒動員で工場に勤務。そこで、歯車製造装置を勝手に改造するなど、その才を遺憾なく発揮してきます。戦後入学した大学では、自動車部に所属。ボロ車を好き放題にいじり回していました。
ところが、就職活動は不調でした。仕方なく、櫻井は1951年に清水建設に入社。しかし、どうしても自動車への夢を捨てきれない櫻井は、給料も良く花形職業だった清水建設を後顧の憂いなく退社。当時貧乏一直線だった、たま自動車の欠員募集に応募します。面接を担当した外山に大いに訝しがられるものの、晴れて合格。櫻井は、胸をときめかしてその一員となります。
櫻井は、トヨタや日産のような大手企業に興味はありませんでした。自らの裁量を活かせる中小メーカーを望んでいたのです。ここから、櫻井は日本の自動車史に燦然と輝く数々の栄光を築き上げていくことになります。
そんな櫻井にとって、プリンスの気風は願ったり叶ったりでした。上下の分別なく議論に熱中し、才能ある若者にどんどんチャンスを与えていく。中島伝統の気風が、依然として強く息づいていたのです。
程なくして、櫻井は日本グランプリ向けのレースマシン開発の中心となり、チームを牽引していくことになります。
徹底した改造と一大物量作戦で、雪辱を期する。
前回の痛い戦訓を生かして、1964年の第2回日本グランプリへ向けて徹底的な改造が行われ、万全の体制で挑むこととなりました。1301~1600ccの車両で争われるT-Vクラス向けには、スカイライン1500を8台。1601~2000ccのT-VIクラス向けには、グロリアを9台。さらに、1001~2000ccのGT-IIクラスにはスカイラインGTを7台エントリー。総勢24台という、物量作戦。その予算はトヨタ、日産の2億円に対し、1.5億円に達したと言われています。
櫻井は早速、スカイライン1500ccの製作に精を出します。外板はすべて0.6mm厚で作り直し70kg軽量化するなど、各部の徹底的な見直しによって200kgを捻出。重量は、700kgまで軽量化されました。サスペンションは硬めに仕立て直し、ミッションも3速から4速に変更されています。
製作された車両を真っ先に走らせたのは、櫻井でした。例え、技術者であっても、自らステアリングを握り、自ら感じなければならない、というのが櫻井の信条だったからです。
レースカーで、悪路の東海道を下る。壊れたら、牽引で帰る。
そうして製作された車両は、次に鈴鹿に持ち込んでの徹底的なテストに供されます。10ヶ月前に始められたテストは、3週間おきに実施されました。と言っても、当時は立派な積載車などありません。参戦車両自らが、サポートトラック等とコンボイを組んで、450kmの道程をひたすら走ったのです。荻窪発は夕方6時、鈴鹿に辿り着く頃にはもう夜が明けていました。
ところが、テストさえまともに走れるようなレベルではありません。2時間ほど走れば、アチコチ壊れます。それでも、無駄骨で終わる訳にはいきません。昼休み返上で必至に修復、午後の走行に備えます。当然、午後も2時間ほど走れば、別のところが壊れます。部品が足りなければ、荻窪に電話。何とか代替品を造ると、荻窪から出発。翌日朝には、届く算段でした。
大変なのは、帰路。まともに走り切れる訳がないのですから、当然、帰路は自走不能となったテスト車両をロープで繋いで、これまた荷物満載のサポートトラックで牽引するしかありません。異常だったのは、翌日そのまま定時まで勤務したこと。残業規制もヘッタクレもありません。昭和の企業戦士、モーレツ社員は、夜を徹して働き続けたのです。
「スカG」伝説のはじまり。〜伝説の名車は、たった3ヶ月で誕生した。〜
グロリアの直6を押し込んだ、おばけスカイライン。

ボディを200mm延長し、直6を押し込んだ怪物。これが、スカイライン伝説の始まり。
By 韋駄天狗 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons
スカイラインで、GT-IIクラスを戦うには、どうしてもパワー不足でした。新開発の6気筒は魅力でも、大柄なグロリアは鈍重でした。しかも、GT-IIクラスにエントリーするには、最低100台の生産が義務付けられています。レースカーまがいのGTカーを作る訳にはいかないのです。
櫻井は、ふと考えつきます。スカイラインに、グロリアのエンジンを載せちゃえばいい、と。これを100台作れば、優勝間違いなし。でも、レースまでたった3ヶ月。たった1度のレースに勝つのに、まったく馬鹿げた提案に違いありません。
ところが、その提案を中川は了承します。役員会での承認は後回しとし、即座に図面作成の開始を命じたのでした。
ところが、スカイラインのボディに長大な直6は収まる訳がありません。そこで、フロントタイヤ後方でボディを切って、ホイールベースを200mm延長。まるで化け物となった、秘密兵器が完成します。その名は、スカイラインGT。
スカG伝説の始まりです。
下位クラスを圧倒する、プリンス勢。しかし、刺客のポルシェ904が登場。
第2回日本グランプリ開幕。本気になったプリンス技術陣の実力は、圧倒的でした。T-V、T-VIクラス共にレースを席巻。上位を完全に独占します。ライバルは軒並み周回遅れ。プリンスは、日本グランプリの制圧に成功します。
ところが、予期せぬ事態が訪れます。本命のGT-IIクラスに刺客が現れたのです。精神医学の先駆者で知られた式場の息子、式場壮一郎が持ち込んだポルシェ904でした。FRP製の軽量ボディは、地を這うように低く、誰がどう見積もってもスカイラインGTに勝ち目はありません。これは、単なる市販レーシングカーだったのです。
プリンスがグランプリを完全制圧するのを阻止すべく、突如登場したその904を見た世間は、その存在を疑います。なぜなら、総生産台数が100台に満たない上、登場間もない904が日本にあること自体が不自然。そこで噂されたのが、トヨタの陰謀。プリンスの成功を阻むべく、裏から手を回したのに違いない、というのです。
当時、トヨタのワークスドライバーだった式場でしたが、鈴鹿を走るのは初めて。加えて、904もシェイクダウンしたばかり。フリー走行は慎重を期して、スカイラインGTの1秒落ちに留まります。ところが、事件は予選中に発生します。
スカG伝説、その始まりの瞬間。観客は熱狂は頂点に達する。
式場は、予選2日目に1コーナーで手痛いクラッシュ。904を、フロントからガードレールに激しくヒットさせてしまったのです。まともなスペアも無い、904。修復は、ほぼ不可能に思われました。
名古屋のガレージに運び込まれた904でしたが、フロントカウルの損傷は酷いものでした。砕けたカウルは、裏から布地を当ててエポキシ樹脂で固め、なんとか成形。しかし、フロントのアライメントは狂ったままでした。
決勝当日、名古屋を発った904ですが、名四国道は大渋滞。このままでは、鈴鹿に辿り着く頃には、レースが終わってしまいます。そこに、白バイが登場。鈴鹿まで先導を頼むと、到着は何とスタート4分前。ところが、本来ならばこれでもDNS。リタイヤ扱いです。プリンス陣営は、激しく抗議します。
主役の奇跡的な再登場。まるで、ドラマの様な筋書きに観客は大熱狂。それもあって、904の決勝出場が許可されます。
スタートから飛び出したのは、やはり式場の904。これを、生沢徹のスカイラインGTが追います。100%とはいかない904を、なだめる様に走らせる式場。ポテンシャルに劣るスカイラインGTを、激しくドリフトさせながら猛追する生沢。そして、7週目。今に語り継がれる奇跡の瞬間が訪れます。
ヘアピンで周回遅れのトライアンフに行き場を塞がれた間隙を突いて、生沢が式場の904を一気にパス。トップを守ったままグランドスタンドに現れたのです。観衆は総立ちの大熱狂。プリンスが、ポルシェを抜いた。その熱狂は、翌日の新聞一面を飾ったのです。
結果は、生沢を抜いた式場が優勝。10秒差の2位には、終盤遅れた生沢をパスした砂子のスカイラインGT。健闘した生沢は、3位に終わります。
後に、様々に語られたこの事件ですが、ここからスカG伝説が始まったのは間違いありません。
プリンスR380の誕生。〜技術者集団が生み出した究極のレーシングプロトタイプ。〜
プリンスの終焉。買収された社員たちは、内部工作で散り散りにされる。
いよいよ、本領を発揮し始めたプリンス技術陣。しかし、その命運は儚いものでした。第3回日本グランプリを前に、プリンスは日産に吸収合併されることを発表。ここから、旧プリンスの面々には過酷な運命が待ち受けていたのです。
日産は、トヨタ同様に激しい労働争議を経験していました。1953年から9月まで続いた日産百日闘争がそれです。そこに暗躍したのが、塩治一郎でした。塩治は別途第二労組を作り、労組の内部対立と切り崩し工作を図っていきます。会社側はロックアウトなど強硬な態度に終始、組合側は会社側の要求を全面的に受け入れるという完全敗北に終わります。労働争議を終結に導いた塩治は、社長の川又克二と完全に癒着。人事はすべて塩治を通すという、日産内に歪な労使協調体制が構築されます。
ここに吸収合併されたプリンスの労働者たちも、塩治らの激しい内部工作にさらされます。彼らは、2つある日産労組のどちらかに属するかの選択を強いられ、袂を分かった面々は激しい対立を始めます。給与体系が安い日産側に統一される事もあって、この時点でかなりの人数がプリンスを去っていきます。
この歪な労使協調路線は深刻な内部対立を招き、最終的には日産を破滅へと導いていくのです。その解決は、カルロス・ゴーンの登場を待たねばなりませんでした。
高速化時代の幕開けと、レーシングプロトタイプへの挑戦。

東海道新幹線と名神高速。日本に高速化時代が到来した。
作者 Szilas [CC0], ウィキメディア・コモンズより
スカイラインGTの成功によって、プリンス社内には自信が芽生えていました。と同時に、ポルシェに負けた悔しさの方が時とともに大きくなっていました。名神高速の開通に続いて、東名、中央と全国に高速道路網が広がりつつあり、東海道新幹線は最高速度210km/hで東京と大阪を結んでいました。時代は、高速化時代を迎えていたのです。
次は、ポルシェを倒したい。プリンス技術陣が、レーシングプロトタイプの開発に歩みを進めたのは、極自然なことでした。
1964年初夏、役員会にてレーシングプロトタイプの開発が承認されます。基本構想として、車両はFIAのグループ6に沿ったレーシングプロトタイプとし、エンジンはウェーバーキャブ3連装の2,000cc直列6気筒DOHCをミッドに搭載、鋼管スペースフレームにアルミニウム製ボディを架装することとなりました。名称は38番目の計画であることから、R380と名付けられます。
日本初の本格的レーシングスポーツは、トヨタでも日産でもない、プリンスから誕生することになったのです。
伝説の名車。プリンス最期の作品。R380の誕生。

前年のスカイラインとは、隔世の感がある。流麗なフォルムを持つ、R380 A-I型。
By Mytho88 [GFDL or CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons
ただ、本格的なレーシングプロトタイプをゼロから造るのは無理と判断、1964年6月の海外視察の折に見てきたブラバムBT8Aを購入。これをベースとすることを決定します。ところが、BT8Aは直4の搭載を前提にしていたため、フレームやサスペンション等は直6への換装を考慮して強度計算をしなおし、大幅な補強が行われました。この辺りは、戦前の航空技術が生かされています。
エンジンは、グロリア用の6気筒ではなく、新規に開発されるGR8型を採用。ボア・ストロークは82.0×63.0mm、圧縮比は11.0。給排気系は8000rpmに脈動効果が最大となるようチューニングされ、潤滑方式はドライサンプとされました。最大出力は、200bhp。組み合わされるトランスミッションは、ヒューランド製の5段が採用されました。
翌年の日本グランプリに間に合わせるべく、R380の開発は突貫工事で進められていましたが、第3回日本グランプリは鈴鹿サーキットとの契約が不調となり、中止。開発は幾分スローダウンしつつも、着々と準備を進めていきます。結局、1965年は開催されず、1966年5月に新設の富士スピードウェイで開催されることが決定します。
1965年4月、荻窪でGR8型エンジンの初号機が完成。9月には早くも目標値を超える205bhp/8400rpmを記録。6月末には、三鷹の試作課で1号車が完成。アルミ地肌の無塗装のまま、村山工場のテストコースに運ばれたR380は、7月3日には櫻井の手によってシェイクダウンが行われています。その後、テストは谷田部の自動車高速試験場に場所を移して継続、細かいトラブルにも順調に対策が行われていきます。
R380-I型での、速度記録への挑戦。
R380の開発は順調でしたが、レース本番は半年も先。そこで、東京モーターショーに展示する際に、技術水準の高さをアピールすらめに、1965年10月6日に谷田部で速度記録への挑戦が実施されます。当日、プリンスの面々はマスコミと招待客を招くほどの余裕を見せていました。
中川が振り下ろす日章旗のもと、R380は猛然とスタート。ハイペースで周回を重ね、最高速度255km/hをマーク。50kmは、国際記録を超えるハイペース。50マイル、100kmでは下回るも、100マイル、200km、1時間では、再び国際記録まで巻き返します。そして、いよいよ200km目前となった頃、左フロントに以上が発生。コントロールを失ったR380はクラッシュ、裏返しになった所でストップします。原因は、左フロントサスペンションのロアアームにあるピロボールの破損でした。
10月14日、諦めない面々は再び記録に挑みます。今回は前回を上回るペースで周回を重ね、50kmまでは快調。ところが、今度はトランスミッションでオイル漏れが発生。敢え無くリタイヤとなります。
2度のトラブルに見舞われたものの、東京モーターショーでは6つの記録が国内記録として公認され、技術のプリンスをアピールすべく華々しいデビューを飾ったのです。
第3回日本グランプリを目指す、R380 A-I型が登場。

R380に搭載された、GR8型エンジン。たった2000ccから、220hpを得た。
By Morio [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
I型と呼ばれたこのR380は、あくまで試作車。1966年の日本グランプリに向けては、新たにA-I型と呼ばれるアップデート版が製作されます。
当然ながら、スペースフレームは完全プリンス製。ブラバムが厚肉小径の鋼管だったのに対し、プリンスは新たに薄肉大径の鋼管を採用。上下左右のフレームがオイルと冷却水配管を兼ねていたのを、独立した配管に移設。軽量化と高剛性化を図りつつ、信頼性の高い設計に変更されています。サスペンションは、ダンパー銘柄をトキコに変更した他、各部の強化を実施しています。燃料タンクはアルミ製から100Lの航空機用のラバー製に変更しつつ、高G下でも偏りしないよう対策が施されました。
フロントカウルは、新たにFRP製を採用。谷田部ではフロントのリフトが問題になったため、これを低減すべくフロント廻りの形状が見直されています。リヤカウルのアルミ製のままながら、デザインは大きく変更され、楕円形のエアインテクを持つ流麗な形状とされました。
エンジンは富士スピードウェイのコースレイアウトを考慮して、新たに仕立て直されています。ピーク領域を6000rpmに下げつつ、よりフラットなトルク特性とされました。その一方で開発が進んだ結果、その出力は220bhp程度まで向上していました。
全開で、30度バンクに突入せよ。1分59秒台に突入した、R380。
1966年3月、富士スピードウェイでのテスト走行が開始されます。ところが、タイムが思ったより上がってきません。ドライバーたちにはレーシングプロトタイプの経験が無かったからです。当時のバイアスタイヤはグリップ限界が低く、ツーリングカーはブレーキも貧弱で重心も高かったため、コーナーでは横向きにドリフトさせて走っていました。ところが、このドライビングはレーシングプロトタイプには向いていません。コーナーではしっかり減速し、スムーズに走らねばならないのです。
プリンスのシミュレーションによれば、1分59秒台が可能との判断でした。しかし、ラップタイムは2分7秒台で足踏み。その原因を詳しく分析すると、ホームストレートエンドから30度バンクに進入する際に減速していたことが分かりました。櫻井は、データを見せてドライバーを説得。やっと、全開で30度バンクに進入できるようになります。グランプリ直前には、生沢が想定通りの1分59秒台のタイムをマークするまで、熟成が進められました。
最終決戦となった、プリンス技術陣。再び、最新のポルシェが立ちはだかる。
完全なるレーシングプロトタイプを準備したプリンスに対し、トヨタと日産は様子見を決め込んでいました。トヨタは、アルミ製ボディに作り変えた2000GTを2台、日産はヤマハ製の6気筒に積み替えたフェアレディSを1台エントリー。対するプリンスは、4台ものR380を投入。必勝体制でこれに望みます。
ところが、再びポルシェの脅威がプリンスを襲います。滝進太郎が、さらに新しい906を持ち込んだのです。エンジンは水平対向6気筒へ進化し、最高出力は30bhp向上の210bhp。車重は、たった575kgしかありませんでした。プリンスのシミュレーションでは、1分58秒台が可能との結果。
既に日産への吸収合併が決まっていたプリンスにとって、第3回日本グランプリは最終決戦の場となるのです。
予選は、雨に見舞われます。車重が軽すぎるR380と906はタイムが出ず、2000GTとフェアレディSが予選上位を占めます。5月3日決勝、前日と打って変わって快晴。期待高鳴る観衆は、9万人の超満員。スタート時間が迫るにつれ、サーキットを興奮が包み込んでいきます。
9万人の大観衆。プリンスR380が、遂にポルシェを破る。
午後2時35分、決勝スタート。トップで30度バンクに進入したのは、生沢のR380。これに、砂子のR380が続きます。トップに立った生沢はミッショントラブルでペースが上がらず、砂子が2周目にこれをパス。生沢は滝を執拗にブロックして、砂子のサポート役に徹します。6周目に何とか生沢をかわした滝は、25周目には砂子もパスしてトップに立ちます。ピットに入る31周目には、その差は8秒まで開いていました。ところが、プリンス陣営には秘策がありました。給油装置です。滝が50秒以上掛かったのに対し、砂子はたった15秒でピットアウト。難なく、トップを奪い返します。
43周目、滝が最終コーナーでクラッシュしてリタイヤ。生沢も、46周目にはストップ。一縷の望みを掛けて、ピットまでマシンを押して戻る生沢には拍手と罵声の双方がたっぷり浴びせられたのでした。
砂子は、そのまま独走で優勝。2位は、同じくR380の大石。3位は、何とか無給油作戦で一矢を報いた細谷の2000GTが入賞しました。
最新のポルシェさえも圧倒する、プリンスの強さ。その姿は、観客を大いに熱狂させます。日産の軍門に降るプリンスでしたが、その技術は日本一であることは、誰の目にも明らかでした。1966年8月1日、遂にプリンスのその名が消える日がやってきます。幸いなことに、プロトタイプレーシングの活動は継続が決定します。
進化を遂げる、日産R380。〜更なる高みを目指して、A-II型の戦い。〜
次なる挑戦へ向けて、「日産R380」はA-II型へ進化。

風洞実験の結果を反映し、近代的なボディ形状へ変更された、日産R380 A-II型。
作者 Iwao from Tokyo, Japan (Nissan R380 II)
[CC BY 2.0 ], ウィキメディア・コモンズ経由で
第4回日本グランプリへ向けて、「日産R380」はさらなる発展を遂げ、A-II型に進化します。
スタイリングはグループ6の規定変更に合わせ、ティアドロップ形状の流麗なルーフ形状となったのに伴って、ドアはガルウイング式に変更。新たに全FRP製となったボディは、風洞実験を反映して空力的に煮詰められました。
鋼管スペースフレームはさらなる大径薄肉化が進められ、強度と剛性が引き上げられました。エンジンは、動弁系や運動部品の材質変更等により、出力向上と軽量化を実施。出力は230bhpへ向上、車重は590kgまで軽量化が進みました。組み合わされるトランスミッションは、よりトルク容量の大きいZF製を新たに採用。タイヤはファイアストンに変更すると共に、大幅にワイド化。操縦性の向上を図っています。
ドライバーの布陣は、大幅に変更されています。日産との合併に伴って社員ドライバーが不可能となったうえ、生沢が欧州へ旅立ったため、横山、砂子、大石の3人が継続。日産からは、ホンダ契約ライダーだった田中健二郎、高橋国光、北野元と新たに契約することになりました。事前テストでは、早くも1分58秒台をマークするなど順調な仕上がり。ただ、砂子と北野がクラッシュを喫するなど、不安もありました。紆余曲折の末、R380は高橋、北野、砂子、大石の4人に託されることになりました。
万全の日産勢に、全面戦争を挑んだのはトヨタではなく、今年もポルシェでした。906が、3台も出場したのです。その内の1台は、何と生沢。欧州から戻った生沢は、R380のドライブを希望したものの、日産にその余地はありません。そこで、自らスポンサー集めを行ったうえ、三和自動車のサポートで出場することになったのです。ポルシェ勢は、本社からメカニックを招聘するなど、本気度が伺える体制を構築していました。
生沢が駆るワークスサポートのポルシェと、大激闘。
予選で速さを見せたのは、進化を遂げた生沢の906でした。たった5周で、1分59秒43をマーク。対する、日産勢は60周の決勝を睨んで、マシンを温存する策を採ります。高橋が3位、北野が5位、砂子が6位、大石は7位からのスタートとなります。
5月3日決勝スタート。飛び出したのは、酒井と生沢の906。これに安田のローラが続きます。R380は、その後方から追い上げを開始します。ところが、1周目のS字コーナーで大石がガードレールに接触し、早くも後退。さらに、最終コーナーで安田がスピン!これを避けるため、砂子と北野も後退。高橋は孤軍奮闘、2台のポルシェに挑んでいきます。高橋は、16周目には906に追いつき、生沢にプレッシャーを掛けていきます。すると、18周目のS字の進入で生沢がシフトミスから、スピン!驚いたのは、高橋の方でした。コース外でストップした高橋が再スタートに手間取る中、先に生沢がコースに復帰。この瞬間、日産勢の勝利の可能性は潰えます。レースは、生沢の独走優勝。高橋はピットイン後に激しく追い上げて、何とか同一周回でチェッカー。2位に入賞します。
再び、速度記録へ挑戦。
この敗北の後、1968年の日本グランプリへ向けて大排気量エンジン搭載マシンR381の開発が決定。R380は、そのバックアップ役を担うことになります。ただ、R380の進化は続きます。主に空力面の向上を図ったA-II改型は、谷田部のスピードトライアルに投入。見事、7つの国際記録の樹立に成功します。
さらに、1968年の日本グランプリには信頼性に不安の残るR381のバックアップとして、3台のA-III型が投入されます。タイヤはさらにワイド化され、新たにダンロップに変更。空力面は一層の進化を果たし、グリップも向上していました。優勝は、北野の駆るR381。これに続いて、黒澤のA-III型が3位に入賞しています。
唯一の海外挑戦。R380 A-III改型が、豪州に遠征。
R38シリーズは、1969年に唯一の海外進出を果たしています。日産陣営は、かねてより海外進出を夢描いていましたし、最終目標はルマンにありました。ただ、トヨタ、ポルシェとの激烈な日本グランプリの戦いは苛烈を極め、到底海外レースへ参加する余裕はありませんでした。たった、1度その望みが叶ったのが、1969年11月2日にオーストラリアで開催されたシェブロン6時間耐久レースでした。
投入されたのは、最終進化型のA-III改型。フロントエンドは、ライトの4灯化によって大幅に変更。ノーズを130mm延長して、大幅に低められました。エンジンも245bhp以上を確実にマークするとともに、連続20時間のベンチテストもクリア。さらに、海外遠征へ際してタイヤをさらにサイズアップ。R380は、大幅にポテンシャルを増していました。レースは、ライバルが早々に脱落したために、見事に1-2フィニッシュ。しかも、257周という周回数はこのレースの新記録でした。
5.5LV8搭載の怪鳥。R381の開発。〜エンジンは何と外部調達。〜
5LV12の開発が間に合わず、エンジンはシボレーのV8を採用。
1967年の敗北を受けて、日産内ではR380の継続開発とともに、全く新たな大排気量の新型プロトタイプの開発を決定します。RXと名付けられたそのマシンは、5LV型12気筒という化け物エンジンを搭載する計画でした。しかし、その時点ではV12エンジンの影も形もありません。翌年の日本グランプリに間に合わせるのは、不可能。そこで、日産は重大な決断をします。
エンジンを外部調達したのです。櫻井は在日米人を介して、北米のチューナーとコンタクト。日産の「秘密兵器」は、シボレーの市販車用5.5LV型8気筒OHVをレース用に仕立てたもので、460bhpを発揮しました。ところが、このエンジンが曲者で、トラブルが頻発。櫻井の頭痛の種となります。
リヤにそびえる、2枚の巨大ウイングが羽ばたく。

リヤにそびえる、R381の2枚のウイング。コーナーで迎角が変化する仕掛け。
I, 天然ガス [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5 ], from Wikimedia Commons
正式には、R381と呼ばれたこの新型マシンは屋根付きのグループ6仕様で、基本的にはR380のスケールアップ版でした。鋼管スペースフレームは、強度と剛性が大幅に引き上げられたものの、基本設計は変わっていませんでした。ただ、フレームはその剛性を高めるために、フロアやバルクヘッドにアルミハニカムパネルを接着する新たな試みが行われていました。
R381の最大の進化は、空力でした。まず目を引くのは、マシン後方にそびえる2枚の巨大ウイング。エアロスタビライザーと呼ばれたそれは、アメリカのシャパラル2Eにヒントを得たもので、独自の進化として左右独立で迎角を変化させられるメカニズムを組み込んでいました。サスペンションがロールすると、イン側の迎角を大きくし、タイヤの接地力を高めます。さらに、ブレーキング中は左右両方が立ち上がってエアブレーキの役目を果たしていました。
屋根なしのグループ7仕様に、突然の設計変更。
R381の開発は順調とはいえませんでした。3月に完成した1号車は、雨の中で大クラッシュ。テストの再開は、3月末の2号車の完成を待たねばなりませんでした。ただ、このクラッシュが思わぬ、チャンスを与えます。1号車を、屋根なしのグループ7仕様として修復したのです。グループ7は空気抵抗のデメリットはあるものの、車重制限やヘッドライト、スペアタイヤ等が不要なため、メリットが多かったのです。新1号車をテストした所、結果が良好だったため、残りの2台もグループ7仕様としてレースに参戦することになります。
1968年の日本グランプリはTNT対決と呼ばれ、史上空前の盛り上がりを見せていました。トヨタ、日産、そしてプライベータの滝・レーシングの三つ巴の構図。一昨年、ポルシェ906で果敢に日産勢に挑んだ滝進太郎が、タキ・レーシングを結成。ニューマシンポルシェ910を生沢に託すと共に、昨年の906に加えて、さらにローラT-70を3台も投入。最強の日産勢に挑戦状を叩きつけたのです。さらには、トヨタも完全なレーシングプロトタイプを開発。オープントップボディに3LV型8気筒を搭載するトヨタ7を4台を投入してきました。
2台がリタイヤするも、北野のR381が圧勝。
予選PPは、前年タイムを何と9秒も縮める1分50秒88を叩き出した高橋国光のR381。2位も、R381の北野。3~5位にローラが並び、6位にトヨタ7の福澤幸雄、7位はR380の黒澤、8位に砂子のR381が続き、生沢は11位と出遅れます。
迎えた決勝は、昨年より20周多い80周。長丁場のレースとなります。厚い雲の下、レーススタート。飛び出したのは、高橋と北野のR381と田中のローラ。大排気量の3台が熾烈なトップ争いを展開します。ところが27周目、田中のローラがサスペンションを壊してリタイヤ。さらに、高橋もホイールナットの緩みからハブを壊してリタイヤ。北野は、孤独な独走態勢を築きます。その後方には、一旦トヨタ勢が上がってくるも、レーし中盤に立て続けにリタイヤ。結局、北野は全車を周回遅れにする圧勝。2位に生沢が入賞するも、3~6位までを日産勢が独占。戦前予想に反して、日産の完全制圧に終わったのでした。
ただ、北野車のクランクシャフトにはヒビが入っており、実際には薄氷の勝利でした。
本命の巨大V型12気筒搭載マシン、R382。〜500psオーバーのモンスターの誕生。〜
6Lのバケモノ級V12エンジンを極秘開発。

巨大なV12エンジンをストレスマウントする、先進的な設計の日産R382。海外挑戦が果たせなかったことが悔やまれる。
By MIKI Yoshihito from Sapporo City,Hokkaido., JAPAN (NISSAN R382.(1969))
[CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons
翌年に向け、日産では本命の12気筒搭載マシンの準備が着々と進められていきます。レースがこれまでの5月から、10月開催へと変更されたため、十分な余裕をもって開発に望むこととなりました。
ゼロから新規に開発されたV型12気筒エンジンはGRXと名付けられ、1967年10月から開発がスタート。バンク角は60度、ボア・ストロークは88.0×68.0で、圧縮比は12.2:1。総排気量4963cc、DOHC4バルブで挟み角は36度と近代的な設計。初号機は、1968年7月に完成。単体重量は267kgと目標を若干超過するも、ベンチテストでは目標性能を達成。508ps/7600rpm、48.5kg-m/6000rpmを記録しました。テストは順調に進み、12月には520psを超える順調な仕上がり。R381-II型に搭載して、テスト走行が勧められました。
R382と名付けられた車体は、1968年12月に開発がスタート。GRX型エンジンの重量増を考慮して、車体で大幅な軽量化を図ることとなります。スペースフレームの材質は、これまでの鋼製からアルミ製に変更。前後に通貫する4本のフレームは、40mm径の大断面とし、これをベースに大小様々な径のパイプを組み合わせ、高応力が掛かる部分にはアルミ合金パネルを溶接。ほぼ、アルミモノコック構造とも言える先進的な設計となります。さらに、エンジンをフレームに剛結。エンジン自体をフレームの一部として応力を受ける構造も取り入れています。60年代の設計にしては、非常に先進的な設計でした。
ところが、日産技術陣の開発はここに留まりません。トヨタの攻勢を予期したのか、さらなるパワーアップを画策したのです。そこで、排気量を6Lまで拡大したGRX-2型を試作。1969年6月には、本番仕様のGRX-3型がベンチテストで580bhpを記録します。この大胆不敵な秘密兵器は、レースギリギリまで極秘とされました。明かされたのは、レース2日前。トヨタは5L、つまり同じ排気量だと信じて開発をしていました。ところが、実際は違ったのです。トヨタがR382が6Lだと知ったのは、R382がサーキットに姿を現したその後でした。
ポルシェワークスが初上陸。トヨタも5台を投入。しかし、2台のR382が全車を周回遅れにして圧勝。
2年目のTNT対決となった日本グランプリ。日産勢が3台を投入したのに対し、トヨタ勢は、新開発の5LV型12気筒を搭載したトヨタ7を、5台投入 。タキ・レーシングは、ポルシェ本社に支援要請。すると、ワークスチームがドライバーとメカニックごと来日。エースドライバーのジョー・シフェールはポルシェ917を、ハンス・ヘルマンは908/2をドライブします。
予選PPは、1分44秒77を記録した北野。昨年より、さらに6秒短縮する驚異的なタイムです。これに黒澤、高橋のR382が僅差で続きます。対するトヨタ勢が4位以降につけるも、その差は4秒近いもの。ポルシェ勢も準備不足が祟り、不調のまま予選を終えています。
決勝は、この年から120周に延長。ドライバー交代も考慮する展開が予想されていました。10月10日、遂に決勝スタート。
強大なトルクを誇る余り、クラッチに不安のあった日産勢は慎重なスタート。トップに立ったのは 、新進気鋭で売出中の若手河合稔が駆るトヨタ7でした。これにシフェールの917が続きます。ただ、遥かにペースに勝る日産勢は、6周目に高橋がトップに立ったのを皮切りに、12周目までには盤石の1-2-3体制を構築。圧倒的なレース展開となります。
途中、高橋が燃料噴射系にトラブルを抱え交代したものの、120周を万全に走り切ってチェッカー。黒澤、北野の2台のR382は、再び全車を周回遅れにする圧勝。日産勢は、最強の名を欲しいままにするのでした。