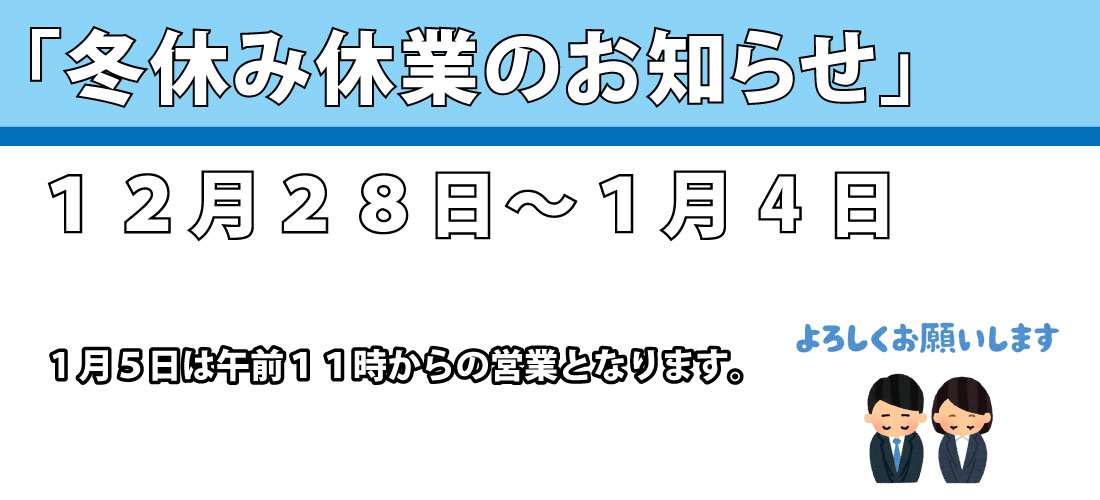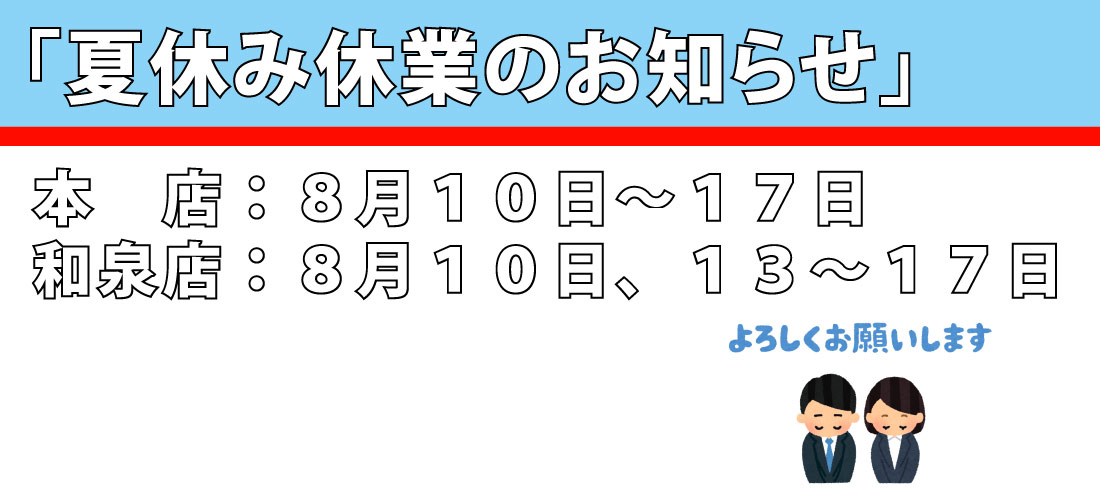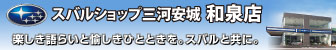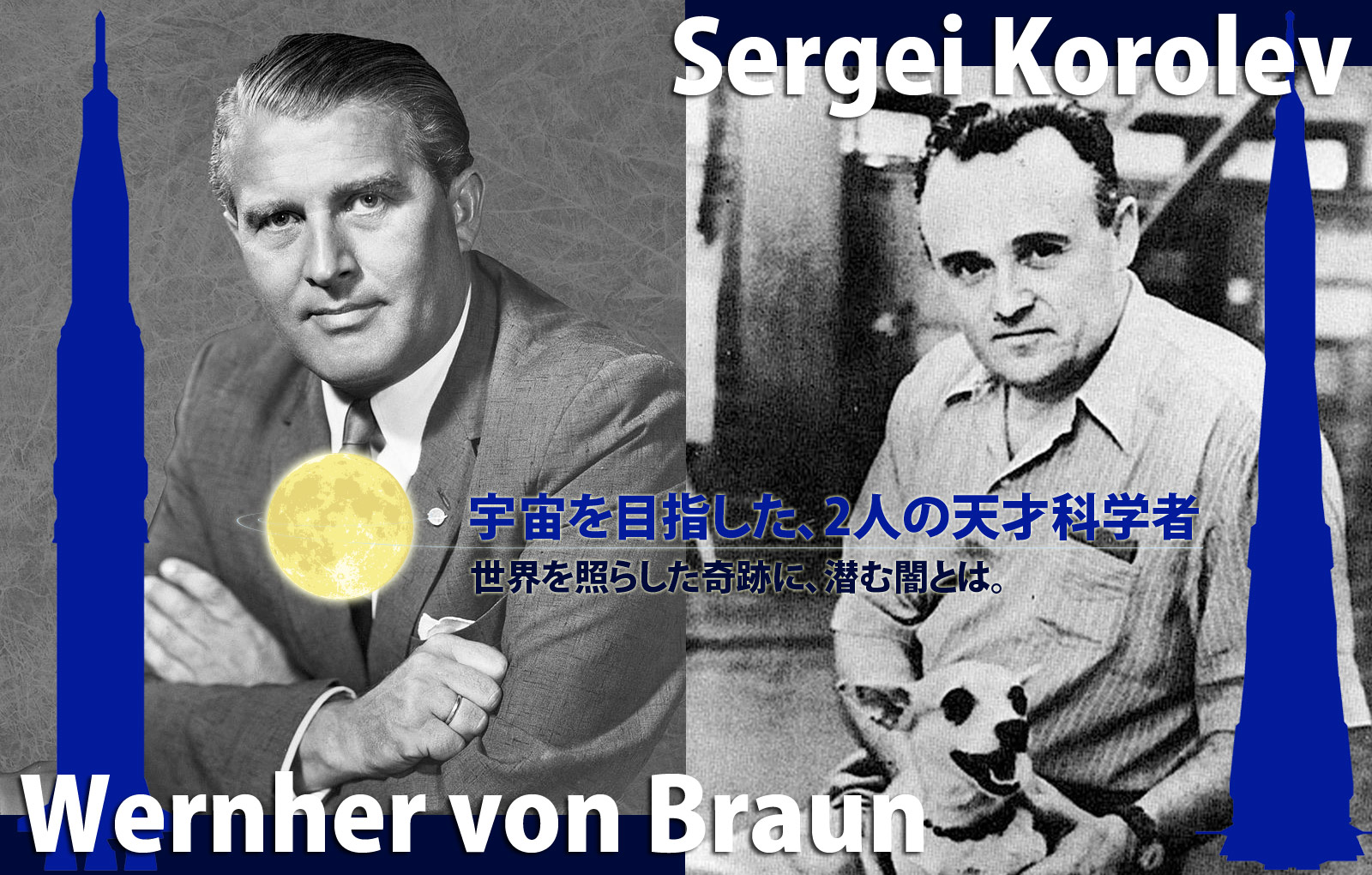ホンダ+日産=?国内自動車産業、再編の先を詠む。 [2024年12月27日更新]
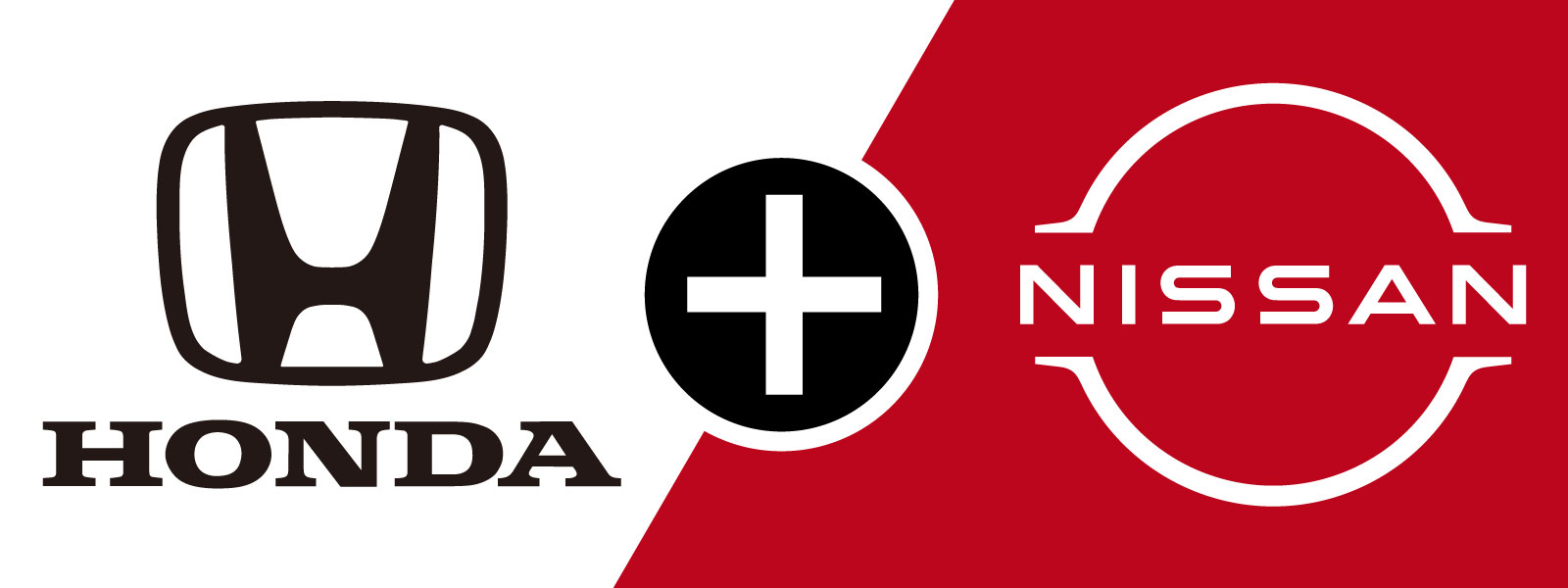
ニュース ピックアップ [ 最新情報 ]
衝撃のニュース満載!!東京オートサロン2026開...
2026年01月10日 スバル
中部自動車販売の冬休みのごあんない。...
2025年12月27日 スバル
スバルが、東京オートサロン2026出展概要を発表...
2025年12月26日 スバル
スバルBEV戦略に大異変!「2025方針」を徹底...
2025年12月12日 スバル
思案に熟慮を重ねに重ね、Youtubeチャンネル...
2025年10月25日 スバル
スバルが遠隔操作型支援器技術を開発って、何のこと...
2025年08月12日 スバル
スバルショップ三河安城夏季休業のお知らせ。...
2025年08月09日 スバル
スバルがBEV第3弾を発表!その戦略を大分析。...
2025年08月09日 スバル
次のページ>>1 2
2024年末、国内自動車産業驚天動地のニュースが飛び込む。
2024年末、驚愕のニュースが国内自動車産業を揺らしています。曰く、「ホンダと日産が、経営統合を検討」とか。長年に渡って、国内普通自動車販売2位の座を争ってきた2社が、軒を同じくする時代が来るとは。。。。901活動や、F1など、双方の華やかなりし時代を見てきた小生としては、実に寂しい限りです。
戦後、二輪を手始めにカリスマ技術者が一世一代で育て上げたベンチャー企業であるホンダ。一方、戦前の発動機製造を手始めに、財閥内の企業合併の中で誕生した日産。その成り立ちからして、全く異なる土壌を有してる2社の経営統合が、今衆目の中で進められようとしています。
ホンダが比較的安定した経営を維持してきたのに対し、日産は幾度もの経営危機を繰り替えしつつも、その度に奇跡的な復活を果たしてきました。しかし、この度の経営危機にあっては、分厚い壁を乗り越えることは遂に叶わず、地面に膝を擦り付ける他なかったのでしょう。明らかにされた合併後の体制を見る限りに於いては、これは対等合併ではありません。ホンダが日産を吸収合併するのに近い状況です。
ここまで、経営統合を急ぐ必要があったのは、台湾の鴻海精密が買収に乗り出しているとの情報があり、経済産業省が他国資本による買収を強く懸念。ホンダに経営統合を急ぐよう強く促したから、とされています。しかし、些か唐突感を否めないのは事実。本当に、この経営統合はうまくいくのでしょうか?
拙速とも思えるこの動きに対し、かのカルロス・ゴーン氏はリモートで記者会見を実施。今回の経営統合に対し、シナジー効果は薄く、意味がないと痛烈な批判を行っています。確かに、ゴーン氏の言う通り、両者のラインナップ/マーケットは完全に重複しており、合併によってビジネスが拡大する要素はないのは事実です。
日本の自動車産業史に必ず刻まれるであろう、この経営統合は果たして吉と出るのでしょうか。ホンダ・日産の背景から探っていきたいと思います。
ホンダには、経営統合の前に成すべきことがある。
ホンダという企業は、実に不可思議な自動車会社なのをご存知でしょうか。ホンダという会社は、本田技研工業と本田技術研究所という2社で、一つのOEMを形成しています。本田技研工業が自動車の開発・生産・販売を行う一方、本田技術研究所は技術開発を担っています。どういう事か、と言えば、技研工業は技術開発に際し、技術研究所に対して開発業務を発注。開発の成果を技研工業に渡す代わりに、技術研究所は対価を貰うのです。実際には、技研工業が各要素技術の開発を、技術研究所の専門チームに委託。技研工業は完成した各要素技術を統合し、新たな車種として開発・生産・販売を行います。
実は、ここに大きな無駄が存在しています。技術研究所と技研工業は一応別会社ですから、業務上の守秘義務が生じてしまうのです。技術研究所にとって、技研工業は「お客さま」ですから、研究所内で勝手にデータや資料を共有することは許されません。例えば、フィット向けのHVシステムを受託した研究所のチームが、シビック向けを受託したチームに対して、データの共有はもちろん、設備の共用さえ許されないのです。
そのため、技術研究所内では、壁を隔てた別チームが、ほぼ同じ内容の開発を「同時並行」で行っていたり、同じ研究設備を重複して導入する事が良くあるのです。限られたリソースを最大効率で管理・運用する。技術系企業では当然の常識的手法が、ホンダでは「別会社」の壁に阻まれてしまう訳です。
なぜ、ホンダはこのような無駄を続けるのでしょうか?ホンダがわざわざ技術研究部門を別会社とするのは、技術研究を商売から分離して自由に行わせる、という本田宗一郎の創業の精神に根ざしています。確かに、ホンダの独自性には、技術研究所の独立性が重要な役割を果たしているように見えます。その一方で、別会社であるがゆえに、技術・設備の重複という大きな無駄も孕んでいるのです。
この度の経営統合により、新たな持株会社が経営を担うようになった場合、技術研究所の独立性はどうなるのでしょうか?このような無駄を覚悟で、経営の独立性を維持するのでしょうか?しかし、経営統合によるシナジー効果を発揮するには、要素技術の共通化は絶対不可欠です。ただ、技研工業と技術研究所の壁さえ越えられなホンダが、果たして日産の壁を越えられるのでしょうか?まず、ホンダが越えるべき壁は、社内にあるように思えてなりません。
日産が抱える深い闇。強権を持つフィクサーの存在。
一方の日産はどうでしょう。日産が抱える大きな問題は、組織内に残る深い傷と歪みにあります。
日産は、幾度も深刻な経営危機を陥ってきました。その最大のものは、1953年に遡ります。日産百日闘争です。当時は、様々な背景から労働運動が活発で、血気盛んな労働争議がアチコチで起きていました。日産百日闘争の労使対立は殊に深刻で、操業は完全に停止。抜き差しならない状況にまで至っていました。
そこに現れたのが、塩路一郎という人物。塩路は、経営側と親密な関係を築きつつ、労使共闘路線を取る第二労働組合を設立。徹底抗戦を止めない労働組合から切り崩し工作を図り、労働争議を終結へと導きます。塩路が巧妙だったのは、経営側ではなく、労働側に身を置き続けたこと。塩路は、社内フィクサーとなることを望んだのです。その結果、人事は塩路の了解がなくては進まないなど、「塩路天皇」の異名を取るほどの権勢を振るうこととなります。
真相の多くは闇の中ですが、1965年には吸収された旧プリンス自動車労働者に対しても、同様の工作が行われています。これに耐えかねた多くの旧プリンス社員が、日産を去っていきました。当の塩路は1980年代に漸く失脚しますが、このような歪な権力構造は日産に大きなシコリを残すこととなります。
この混乱した状況に大鉈を振るうことが出来たのは、一切のしがらみを持たない黒船、カルロス・ゴーン氏だけでした。1999年にルノーからやってきたゴーン氏は、銀座の霞が関と言われた官僚体質を完全打破するため、自らを頂点に戴く強力な中央集権体制に移行。村山工場の閉鎖を含め、2万人以上を削減する大胆なリストラ策を断交。帳簿上ながら早々に黒字転換を果たし、劇的な復活を演出。5年のうちに、株価を3倍に引き上げることに成功したのです。
ただ、大鉈を振るえば、新しい波が立つのは当然のこと。このような背景もあって、日産は常に組織構造の中に歪み(派閥闘争)を抱えてきたのです。
ゴーン氏がもたらした功罪、異様な権限を有する購買課。
確かに、カルロス・ゴーン氏は日産の救世主でした。大胆なコストカットにより、明日をも分からぬ日産を見事に復活させたのですから。しかし、その中で新しい歪みも生まれます。それは、異様に強力な権限を持った購買課の存在です。かつては「技術の日産」と呼ばれたように、技術開発に積極的でした。それは、設備投資、開発投資、人材投入、高額部品の購入に寛容である、という意味でもあります。
でも、それこそが支出。ゴーン氏は、ここに大鉈を振るったのです。コストカットとは、収入を増やすことではなく、支出を減らすこと。つまり、高いのであれば、買わない。買うなら、安いモノしか買わない。
しかし、ここに日産の致命的な勘違いがありました。日産が「安くしろ!」と言えば、何処ぞの某OEMと同じように、「ヘイヘイ、お館さま」とばかりに、何でも安くなると安易に考えていたのです。しかし、現実は違いました。無理してまで日産と取引するサプライヤは、何処にもいなかったのです。
なぜでしょう?それは、ゴーン氏が早々にケイレツを解体したからです。トヨタのケイレツが無理をするのは、トヨタが安いけれども「必ず買う」という保証を与えるからです。生産量を必ず確保される分、ケイレツは頑張るのです。でも、日産はケイレツをバッサリ切ってしまった。それはつまり、「必ず買う」保証をしない、ということ。そんな状態ですから、無理してまで値段を下げるサプライヤなど存在するはずがないのは当然でしょう。
そんなこんなで、日産車の信頼性はダダ下がり。E12型ノートでは、数万キロでハブベアリング交換が必要になるとか。当然の報いと言うべきか、中古車市場では軒並み激安となる始末。
それだけではありません。購買課の台頭は、技術の停滞を招きます。日産の経営陣が、購買課に計画の不承認さえ許したからです。幾ら必要な設備であっても、購買課が蹴ってしまえば、計画は即キャンセル。当然、エンジニアのモチベーションはみるみる低下していき、離脱者多数・・・。「技術の日産」など昔話。今や、「購買の日産」となって、今や迷走まっしぐら。。。業績悪化も当然の成り行きでしょう。
レアメタルは、今やOEM自身が確保する時代。生き残りを賭けた業界再編。
今回の彼らの結婚は、本当に「望んだもの」なのでしょうか?スズキ、マツダ、スバルがトヨタ色を明確にする中、残されたのはホンダと日産+三菱という図式を考えれば、日産には選ぶ相手がホンダしか居なかった、というのが実情でしょう。トヨタは「国の指図」を何よりも嫌いますし、ルノーとは離婚協議が進んでいる。そこに、鴻海精密の買収が間近に迫っていると経済産業省のゴリ押しがあれば、選択の余地は無かったはずです。
ステランティスを筆頭に、自動車産業の再編が進むのは、シナジー効果を期待してのこと。自動運転の実現に際して必要となる高速演算処理、電動化に際して必要となる大容量パワーエレクトロニクス、コネクテッドの実現に際して必要となる高速大容量データ通信及びサーバ。また、これらに付随して必要となるレアメタルの数々。一気に急増する需要に対し、供給が不足するであろうことは従前から予測されており、これらの生産枠確保にOEMは血眼になっているのです。
SoCのような高度に特殊な部品に限っては、OEM自らが原材料を確保、これをサプライヤ側に供給した上で、部品供給の確約をさせる、という事例まであるようです。部品がなくては、クルマは造れません。だからこそ、OEMは形振り構わず生き残りの術を探っているのです。
ここで効果を発揮するのが、大規模企業連合です。一定以上の購入枠を保証することで、OEMはより確実に(できれば安く)、より安定した調達を確保することを企図しているのです。ステランティスなどは、その象徴的存在であると言えるでしょう。
部品・原材料調達先確保に限って言えば、今回の経営統合は大きなシナジー効果を発揮することでしょう。世界第3位のOEM連合が誕生するとなれば、供給側も決して無視出来ぬ存在となるからです。
ファンこそが、ブランド存続の鍵。大切にしたホンダと冷遇し続けた日産の差。

2021年発売の3代目キャッシュカイは、英国向け右ハンドル仕様があるにも関わらず、国内未発売。日本市場放置の象徴的モデルの一つである。Alexander Migl, CC BY-SA 4.0
ただ、これだけでは経営統合のメリットも半減です。莫大なコストカットを実現するであろう、技術面の統合が不可欠です。新たな企業連合が誕生するにしても、全く別のコンポーネントを用いて、全く別の車種を生産していては、殆ど意味を成しません。技術の一本化を含む、大胆な統合策が必要不可欠でしょう。スバルが結局はTHSを採用せざるを得なかったように、電動化には莫大な開発投資が必要です。これらの技術を、ホンダ・日産が各々自前で開発していたのでは、全く意味がないのです。
電動化、自動運転、コネクテッド等、自動車技術はまだまだ多くの発展の要素を有しています。日産のバッテリ技術とホンダのFCV関連技術など、相性の良い分野も多く存在しますから、こうした先端分野については逸早く統合し、開発を促進すべきでしょう。
ただ、技術統合は経済評論家からは万々歳でしょうが、消費者目線で見れば大不評でしょう。ホンダにしろ、日産にしろ、固定ファンを多く持っているOEMですから、統合によって技術的個性が失われ、かえって裏目に出る可能性もないとは言えません。
まぁ、確かにそのような消費者は少数ですから、売れるクルマを造れば良いんだ。そう仰る方も多いでしょう。ただ、スバルやマツダが細々ながらしっかりと生き永らえてきたのは、技術的個性と固定ファンを維持してきたからこそ。技術的個性を失い、ファンを失えば、OEMのブランド価値は間違いなく危機に瀕するでしょう。そもそも、ホンダの経営が安定しているのも、日産が危機に瀕したのも、ファンの扱い方の違い、と断じるのは言い過ぎでしょうか。
日産は、「グローバル」「グローバル」と呪文如く唱え、国内モデルを古いまま放置し、ファンを失望させ続けてきました。マーチ(欧州名:マイクラ)では、英国向けに新型が存在したにも関わらず、旧型の販売を継続した上にモデル廃止。コンパクトSUVの国内投入に際しては、英国向けのキャッシュカイではなく、何故か中南米市場向けのKIXを導入。その上、旧型のまま放置し続けています。この他にも、国内で売れるであろう海外専用モデルが存在しても、何故か国内導入を見送り、わざわざ日本のファンを失望させる「仕打ち」を続けてきたのです。このようなファン無視の経営方針では、今の状況も致し方ないように思われてなりません。
ホンダ・日産を苦しめる、フルラインナップという足枷。


北米市場向けに巨大なピックアップトラックをラインナップするホンダと日産は、共にフルラインナップメーカーである。Elise240SX, CC BY-SA 4.0
このように問題を抱えた両者ですが、経営統合に本当に意味はあるのでしょうか?ゴーン氏の指摘するように、ラインナップが重複する経営統合に意味はないように思えます。
ホンダと日産の双方に共通するのは、頑ななグローバル展開です。米国、欧州、中国、アジア、中南米、日本と、6つの市場を考えたとき、最も効率が良いのは同じ車種を全世界に供給すること。そうすれば、1モデル当たりの販売台数を増やせますし、ラインナップを最小限に絞ることも可能です。ただ、世の中そう簡単ではありません。発展途上国では価格が第一ですが、日米欧市場ではクォリティと信頼性が第一。中国市場では、現地生産のEVであることが条件となります。そのため、各市場に適合するモデルを各々用意せねばならないのです。
これに対し、スバルとマツダは全く同じ戦略を採っています。それは、グローバルモデルで参入不可能な市場ならば諦める、というシンプルなもの。確かに、この戦略の方が理に適っているように思えます。新規車種の開発には莫大な費用が必要ですし、生産拠点・サプライチェーンの海外展開を考えると、それ程世界販売に旨味があるようには思えないからです。
しかし、国内2位を自称するホンダと日産は、トヨタを追いかけるように、頑なにグローバル展開を維持。米国では大型SUVとピックアップ、中国にはBEV、アジア・中南米には戦略車種、日本では軽自動車を用意。結果的に、膨大なモデルラインナップ(つまりは、ムダ)を抱えるに至っています。
もし、経営統合によって車種開発が分担が出来るのなら、それは大きなメリットとなるでしょう。プラットフォームの数は、完全に半減。開発費も大いに削減されるからはずだからです。ゴーン氏のように、無いものを求め合う企業合併もありでしょうが、あるもので補い合う合併も決して悪くないように思われます。両者は経営統合により、現在同様の広いラインナップを確保しつつ、世界市場へチャレンジしていくことになるでしょう。
次のページ>>1 2
スバルショップ三河安城 店舗案内

>>最新情報一覧